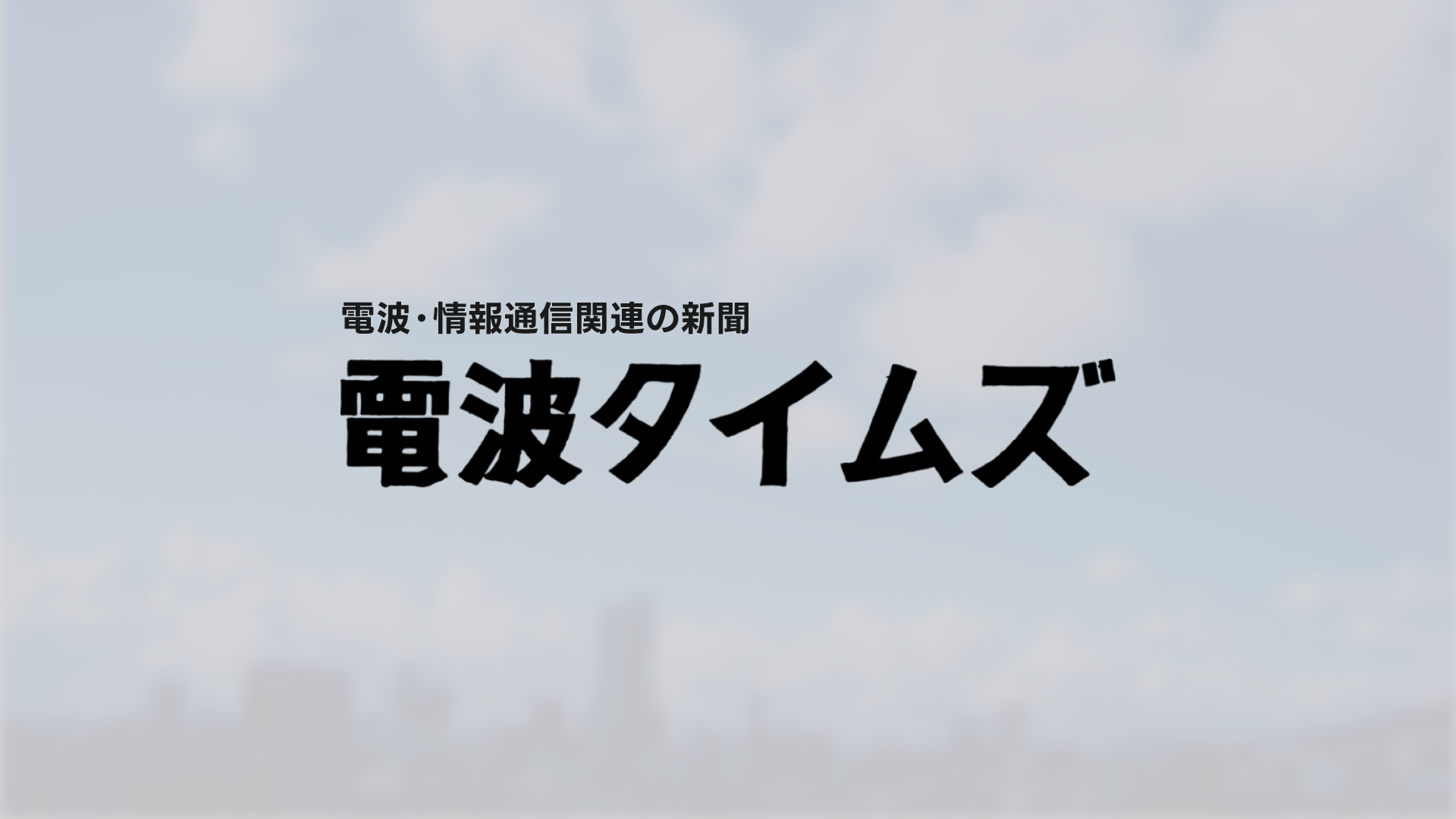
固定系契約数7・9%減、移動系5・3%増
総務省は、電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)の規定に基づき、電気通信事業者から報告のあった令和5年度分の音声通信量データについて取りまとめ、公表した。
国民生活や社会経済活動に必要不可欠なサービスである電気通信サービスの在り方を検討するためには、その利用動向を客観性、信頼性のあるデータに基づいて把握することが不可欠となっている。
このような観点から、総務省(当時郵政省)では、昭和63 年に電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)を定め、電気通信事業者から音声サービスに係るトラヒック(通信量)データ等の報告を求め、電気通信政策の策定等に活用。また、データを国民利用者に公表することにより、電気通信サービスに対する理解を深めることに役立てている。
規定に基づき、電気通信事業者から報告のあった令和5年度分(令和5年4月1日~令和6年3月31日)の加入電話、ISDN、公衆電話、IP電話、携帯電話及びPHSの利用状況について集計・分析を行い、取りまとめた。
内訳は、国内トラヒックが固定系(加入電話、ISDN、公衆電話)関係10者、IP電話関係21者、移動系(携帯電話・PHS)関係11者で、国際電話トラヒックが7者。
報告概要によると、契約数等の推移では、固定系(加入電話・ISDN・公衆電話)全体では、1364万契約・台で対前年度比7・9%減少。加入電話は1183万契約で対前年度比7・3%減少、ISDNは170万契約で対前年度比11・7%減少、公衆電話は11万台で対前年度比9・5%減少だった。IP電話の利用番号数は、4569万件で対前年度比概ね横ばいで、移動系(携帯電話・PHS)全体では、2億2192万契約で対前年度比5・3%増加。携帯電話は2億2192万契約で対前年度比5・3%増加、PHSはサービス終了に伴い対前年度比100%減少だった。
国内トラヒックの推移としては、令和5年度の総通信回数は、602・4億回で対前年度比6・6%減少。令和5年度の総通信時間は、2511・5百万時間で対前年度比11・0%減少した。
国内トラヒックの通信回数について、国内通信の通信回数を発信種類別にみると、固定系発信は73・0億回で対前年度比13・3%減少、IP電話発信は151・0億回で対前年度比3・8%減少、携帯電話・PHS発信は378・5億回で対前年度比6・3%減少した。通信回数の発信種類別比率は、固定系発信が12・1%、IP電話発信が25・1%、携帯電話・PHS発信が62・8%で、固定系が占める割合が低下し、IP電話及び携帯電話・PHSが占める割合が増加した。
(全文は4月7日付紙面に掲載)
この記事を書いた記者
- 主に行政と情報、通信関連の記事を担当しています。B級ホラーマニア。甘い物と辛い物が好き。あと酸っぱい物と塩辛い物も好きです。たまに苦い物も好みます。
最新の投稿
 行政2025.04.07令和7年度総務省人事異動
行政2025.04.07令和7年度総務省人事異動 行政2025.04.07固定系契約数7・9%減、移動系5・3%増
行政2025.04.07固定系契約数7・9%減、移動系5・3%増 行政2025.04.04総務省がフジテレビと親会社に行政指導、中居氏巡る問題の報告受け
行政2025.04.04総務省がフジテレビと親会社に行政指導、中居氏巡る問題の報告受け 行政2025.04.04令和7年度警察庁人事異動・情報通信、サイバー関連
行政2025.04.04令和7年度警察庁人事異動・情報通信、サイバー関連


