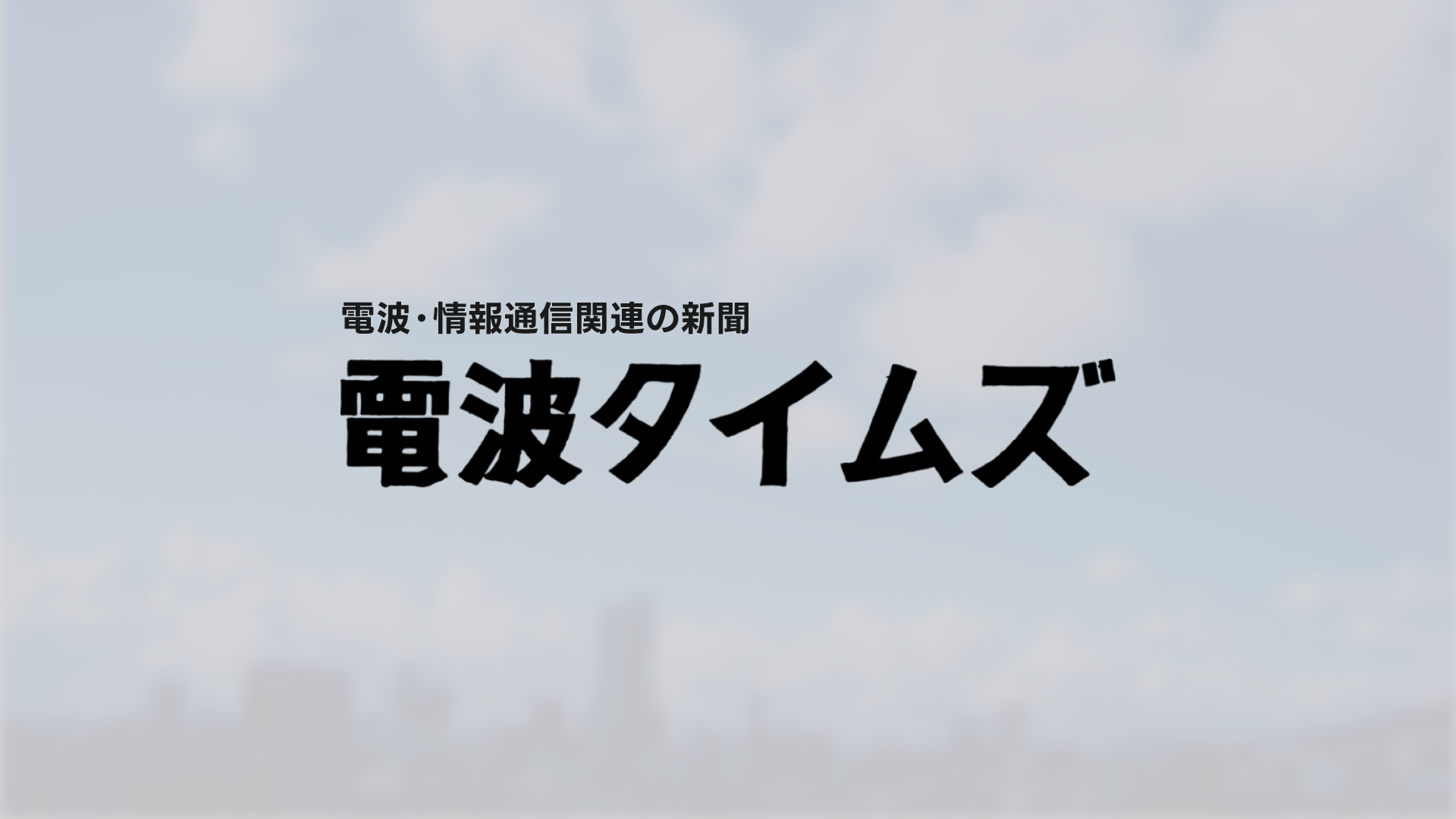
フジテレビ、「浅い思慮により対応方針を決定」と批判
中居正広氏と女性のトラブルをめぐる一連の問題を受けて、フジテレビと親会社のフジ・メディア・ホールディングスは、第三者委員会の調査報告書を公表した。
第三者委員会は、一連の問題で「女性Aが中居氏によって性暴力による被害を受けたもの」と認定し、「重大な人権侵害が発生した」としている。
本事案は、CX(フジテレビ)が番組起用している「有力タレント」による CX 社員である「女性アナウンサー」に対する重大な人権侵害の問題であった。CX は女性 A のプライバシーを守り、その意思を尊重しながら、中居氏の起用継続の可否、その前提となる中居氏への事実確認等の対応を検討、実施することが求められていた。難しい経営判断が必要となる局面であったが、他の取締役、監査役への情報共有・報告、取締役会への報告は行われなかった。また、人権、コンプライアンスの専門家の助言や意見を聴取することもなく、そうした検討すら行われなかったとしている。
結局のところ、本事案への対応方針は、E 氏(編成局事業局長)の最初の報告内容から編成制作ラインの役員・局長クラスの壮年男性 3 名が受けた印象や思い込み(つまり、性暴力に当たる事実の報告を受けたにもかかわらず、2 人で中居氏のマンションで会ったことをもって、「プライベートの男女トラブル」と捉えてしまうという思い込み)をもとに、3 名のみの偏った視点で検討され、多角的な視点からの検討や議論は行われなかった。
港社長ら 3 名は、本事案を、社員が取引先から性暴力を受けた疑いのある事案であり、CX の人権問題と捉えることができず、女性 A の自死の危険性があるということに衝撃を受けて思考停止に陥り、浅い思慮により対応方針を決定したという。
本件は、CXの社員である女性アナウンサー(女性 A)が、同社の番組に出演している有名男性タレント(中居氏)から性暴力による重大な人権侵害の被害を受け、CX は女性 Aから被害申告がなされたにもかかわらず適切な対応をとらず、漫然と中居氏の番組出演を継続させた事案である。
女性 A は、業務復帰を希望していたが、断念して退職せざるを得なかった。事後に週刊誌報道を契機として本事案が発覚したが、CX 及び FMH は本事案への対応についてステークホルダーに対する説明責任を果たすことができず、その結果、視聴者、スポンサー、取引先、株主・投資家、社員その他のステークホルダーから厳しい非難を受け、社会的信用が失墜し、後記のとおり、数多くのスポンサーによる CM の AC 差替え、投資家による抗議、取材先やロケ先における拒否等を受けており、危機的状況に陥っていると厳しく批判している。
また、日枝久氏の経営責任については、「日枝氏は、CX・FMH(フジ・メディア・ホールディングス)の代表取締役会長と代表取締役社長というトップ人事を決めていた。それよりも下層の人事は会長と社長が決めていたが、中には会長と社長が日枝氏にお伺いを立てている状況も見受けられた。
日枝氏は、1983 年に取締役に就任し、1988 年から代表取締役社長、2001 年から代表取締役会長を務め、2017 年から現在まで取締役相談役を務めている。長年にわたる功績と経営中枢への関与から、現在でも当社の経営に強い影響力を及ぼしており、当社の組織風土の醸成に与えた影響も大きいといえる。
当社の代表取締役会長と代表取締役社長というトップ人事を含む役員人事は、本来ならば取締役会による「役員指名ガバナンス」が機能し、対外的な説明責任を伴って意思決定されるべきである。経営諮問委員会を十分に機能させなかったことも含め取締役会がこうした機能を果たしてこなかったことは、日枝氏のみならず取締役会メンバー全員に経営責任が認められる。 港社長の任命責任を日枝氏に問う声もあるが、その任命責任は取締役会メンバー全員が負うべきである。
したがって、当委員会は、当社の経営に対する日枝氏の影響力さえ排除すればコーポレートガバナンスが機能するかのような見方には与しない。取締役会メンバー全員が、役員指名ガバナンスを含むコーポレートガバナンス機能の強化に使命感を持ち、不断の努力を続けていかない限り、当社のコーポレートガバナンス機能の強化は図れないものと考えるとしている。
この記事を書いた記者
- 放送技術を中心に、ICTなども担当。以前は半導体系記者。なんちゃってキャンプが趣味で、競馬はたしなみ程度。
最新の投稿
 実録・戦後放送史2025.04.02「記念すべき6月1日②」
実録・戦後放送史2025.04.02「記念すべき6月1日②」 放送機器2025.04.02富士フイルム、4K対応放送用ズームレンズを新開発
放送機器2025.04.02富士フイルム、4K対応放送用ズームレンズを新開発 プレスリリース2025.04.01デル・テクノロジーズ、Copilot+ PCの実力を最大限に引き出す2つの新サービスを提供開始
プレスリリース2025.04.01デル・テクノロジーズ、Copilot+ PCの実力を最大限に引き出す2つの新サービスを提供開始 放送2025.04.01フジテレビ、「浅い思慮により対応方針を決定」と批判
放送2025.04.01フジテレビ、「浅い思慮により対応方針を決定」と批判


