【放送ルネサンス】第17回:西土 彰一郎さん(成城大学教授)

成城大学教授
西土 彰一郎 さん
西土彰一郎(にしど・しょういちろう)氏。 1973年生まれ。福岡県久留米市出身。1996年神戸大学法学部卒業。2002年同大学院法学研究科修了。名古屋学院大学経済学部講師、成城大学法学部准教授を経て、現在、同教授(専攻:憲法・メディア法)。現在、放送倫理・番組向上機構(BPO)放送倫理検証委員会委員。
西土 彰一郎さん インタビュー
Contents
ご自身にとって放送とはどういう存在か
高校生の頃、ちょうど冷戦構造が崩壊する時期で、ベルリンの壁が崩れるなど様々なことが起き、それをテレビ報道で見ていた。米ソ両首脳が「冷戦の終結」を宣言したのが1989年12月だったが、画面越しにリアルタイムで歴史の場面に立ち会っていると感じた。それがテレビジャーナリズムに興味を持ったきっかけとなった。
その後、大学2年の時、有名な椿事件が起きた(テレビ朝日による放送法違反〈政治的な偏向報道〉が疑われた事件)。 ちょうど日本国憲法の人権について講義を受けていて、まさに表現の自由、表現内容規制(表現行為の観点・主題に着目した規制)がいわれ、テレビや雑誌・新聞で取り上げられた。椿事件も契機として、放送の自由に対する関心が強くなり法律の勉強をしようと大学院に入って研究者になった。
これまで、わが国で放送が果たしてきた役割をどう評価しているか
戦前は、国家目的のために放送が利用され、政府や軍の広報機関と化してしまった。その反省のもとに立って、戦後の放送法制ができあがった。これによって、放送は、国民の知る権利に奉仕してきたと思う。そうした放送の役割の点では、いまも変化はないのではないか。
放送法1条は、公共の福祉、放送の不偏不党、真実及び自律を保障、放送による表現の自由を確保することなどを謳っている。この3項目は国家を義務づけるものとして今後も当然、擁護すべきだ。放送のあり方としても、ネット社会だからこそ、ますます重要になっているともいえる。
ただ、インターネットの普及の下、国民の知る権利といっても、「個人として知りたい情報の提供」よりも、「国民として知るべき情報の提供」の側面に重点をシフトしていくべきだと思う。かつて、NHK第5代会長の高野岩三郎が、1946年4月30日の就任挨拶で「大衆とともに歩み、大衆とともに手を取り合いつつ、大衆に一歩先んじる」と放送のあり方を説いた。今の時代は、特に「一歩先んじる」という、国民として知るべき情報に重点を移していくべきだ。
放送における国家との距離について変化は
かねてより、放送における国家との距離の問題は重要な課題だ。政治的な力が、放送局の放送に影響を及ぼす恐れは絶えずある。放送法4条の政治的公平に関する解釈について、それまでは「政治的公平」は放送局の番組全体で判断するというのが基本的な解釈だったのが、2016年、当時の総務大臣が、場合によってはひとつの番組で判断すると、国会で答弁したことがあった。これを巡って、2023年3月7日、総務省が放送法の「政治的公平」を巡る文書を公開した。
この問題は、現在も焦点となっていて、政権与党に反するような番組内容を流すことに、放送が躊躇し、萎縮してしまう恐れがある。今でも、放送事業者や現場の放送制作者に、萎縮効果を及ぼしている可能性があり、国民の知る権利の充足に影を落としている。
問題は、国会でそういう放送法の解釈変更に関する答弁がなされたときに、さほど報道されなかったことだ。もっと言うと、1993年の椿事件に関しても、放送局や新聞社が、「これは報道の自由に対する介入だ」として、放送局が一致して、立場を超え連携し、政府に対抗したかといえば対抗していない。これは私は非常に怖いことだと思う。そもそも放送人としてどうなのか。他局が政治介入されている時、立場を超えて連携をしないのは、国民の知る権利に奉仕する国民への責任を放送人として果たしているとはいえない。
番組づくりに対して感じることは
テレビも、いわゆるアテンションエコノミーになっているのではないかと感じる。アテンションエコノミーは、情報の質よりも人々の関心や注目を集めた方が経済的利益が大きいことを指摘した経済学の概念だが、放送も、これによってネットでの閲覧数を稼ぐという方向へ移行しているのではないか。閲覧数を稼ぐためにバラエティーやドラマに重点を移し、報道やドキュメンタリーがますます脇へ追いやられている印象を受ける。
ただ、今後の方向性としては、報道やドキュメンタリーといった硬質なものが、むしろ閲覧数を稼げるのではないかと考えている。つまり、「国民として知るべき情報の提供」に番組の重点を移すことが、ネットとの差異化になる。ところが、現状は、国民として知るべき情報の提供がおろそかになり、個人が知りたい情報ばかりに力を注いでいるという印象を持っている。

若者のテレビ離れが進む中、放送終焉の声も聞こえるが
「放送は生き残れるか」と、よく問われるが、私は放送は生き残れると考えている。理由は3つ。ひとつは、ネット上では偽情報や不正確な情報、誹謗中傷が溢れているが、そういう環境だからこそ、職能としての放送人が放送倫理を基に、取材・編成・考査等を経て慎重に制作した放送番組への需要は高いはず。これは世代を超えた要求だと思う。2つ目は、こうした職能としての能力は、若者の知的好奇心を満たす番組制作を可能とするはずだということ。3つ目は、国民の知る権利に奉仕してきた放送に対する信頼は歴史的にも厚い。そうした放送の伝統があるのだから、ネットにびくつくことはない。ただし、それは今の放送全体というより、放送ジャーナリズムについてであり、「放送ジャーナリズム」は生き残るという意味だ。
そのために、放送ジャーナリズムはどうあるべきか
80年代以降、視聴者の注目を集めることを目的とする覗き見趣味的なワイドショーや報道情報番組が増えてきた。それはネット社会の先取りだったかもしれないが、今後も、こうした娯楽番組的なものに重点を置くのであれば、放送はネットに飲み込まれるだろう。
ネットでは、個人として見たい知りたいことが優先されるが、放送は、まさにそうしたものに対して反省してきた歴史がある。放送倫理を明確にさせ各放送局がそれをきちんと鍛えてきた。今後は報道・ドキュメンタリーといった、放送ジャーナリズムを伸ばしていくこと、もっと言えば、調査報道をしっかり手掛けていくことだ。手間隙かけて真実を追う、隠れた真実を掘り起こす調査報道に放送の未来があるのではないか。それに対する需要は若い世代も含めて高いと考えている。
ネットの普及によってネットが放送に置き換わっていくという見方もあるが
放送の法的概念をどう見るかにもよるが、取って代わることはないと思う。私の専門のドイツを参考にすると、憲法上の放送概念を構成する要素は、「公然性」、「表現手法」、「情報通信技術」の3つとなっている。「公然性」とは、大衆を対象にしていること。「表現手法」とは、放送法上、ジャーナリズム的編集と定義されている。つまり、放送を構成する「表現手法」は、ジャーナリズムであるとしている。そう考えると、ジャーナリズムという「表現手法」に注目すれば、放送はネットに吸収されることはない。
日本もジャーナリズム性にますます重点を置いて、放送法を含めて放送の役割を評価していくべきではないかと考えている。そして、そのジャーナリズム性とは、国民として知るべき情報の提供であり、具体的にいえば調査報道であり、そうした方向へ持っていくべきではないか。それは、ネットによって置き換えられることはない。
伝送路としての放送はネットに置き換わるか
いまお話したように、ドイツでは放送概念を構成する要素の一つに「情報通信技術」とあるが、言葉通り、そこには、放送波とか通信とかは関係が無い。その意味では、放送は、すでにネットに置き換えられているかもしれないが、そこが問題ではなく、置き換えられないのは「表現手法」であり、ジャーナリズムということであり、ジャーナリズムの実現に最適な通信技術を選べばよいということになる。放送として重要なのは、組織ジャーナリズムであり、日本でいえば、放送法4条がポイントになると思う。これを遵守するジャーナリズムは放送にしかないものであり、放送法4条と、それを自らの倫理規定として守って行くことを、しっかりアピールすることが、放送の存在意義となるはずだ。
「プロセス的放送概念」ということを話されているが、その意味は
情報通信技術が進展する中で、立法者はメディア環境を観察しながら、放送ジャーナリズムの実現に最適な情報通信技術を試行的、暫定的に「放送」として概念化していくべきであるという意味だ。個人情報保護法上の見直し規定のように、法制度上も、ジャーナリズムの観点に立った未来志向でのもと、放送概念を柔軟に変えて、社会情勢の変化に迅速に対応していくべきだと考える。
放送とネットの関係について
かつて、鶴見俊輔氏が「ジャーナリズムとは何か」に関して「毎日の記録がジャーナリズムであろう」と云っている。つまり日々の一人ひとりの個人が日常生活であったことを記録していく、それがジャーナリズムだと。そこに今後のジャーナリズムの可能性があるのではないかと思う。
ネットには玉石混交の情報が流れているが、「玉」の部分としては、個人が自分の日常生活を日々記録しているような情報もある。放送が、それと連携してジャーナリズムを鍛えていく。そういう参照点の提供というのもあっていいのではないか。そこにジャーナリズムの再構築のヒントがあるのではないかとも思う。
放送への提言・注文・期待があれば聞かせてほしい
放送人の好奇心が最も大事だと思う。現場の制作者など放送人であれば、だれでも一人ひとりに知りたいことがあるはずで、それが放送の原点となる。その好奇心さえあれば、外野の意見は気にならず、上司の圧力も、政治家の圧力も、全く関係なく、知りたいこと、やりたいことをとことん追求していくことができる。放送は、そういう組織体制であってもらいたい。そのための組織を作ってほしい。つまり風通しの良い組織だ。
報道機関のあり方をめぐっては、「内部的自由」という議論がある。現場のジャーナリストの自由を組織が認め守っていくことが重要だ。本当はNHKが、それを一番よく実現できる組織のはず。自分の好奇心で仕事が行える職場であることが、今後、放送文化として生き残っていく道ではないかと考えている。
残っていく道ではないかと思う。
この記事を書いた記者
- 元「日本工業新聞」産業部記者。主な担当は情報通信、ケーブルテレビ。鉄道オタク。長野県上田市出身。
最新の投稿
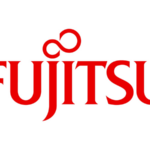 情報通信2025.12.26富士通、AIエージェントをシームレスに連携
情報通信2025.12.26富士通、AIエージェントをシームレスに連携 CATV2025.12.26自由が丘にイッツコムサービス体験窓口店舗
CATV2025.12.26自由が丘にイッツコムサービス体験窓口店舗 情報通信2025.12.26日立、自社クラウド基盤上でMES 導入テンプレート
情報通信2025.12.26日立、自社クラウド基盤上でMES 導入テンプレート CATV2025.12.25上田ケーブルビジョン、北向観音「護摩」ライブカメラ
CATV2025.12.25上田ケーブルビジョン、北向観音「護摩」ライブカメラ
本企画をご覧いただいた皆様からの
感想をお待ちしております!
下記メールアドレスまでお送りください。
インタビュー予定者
飯田豊、奥村倫弘、亀渕昭信、川端和治、小松純也、重延浩、宍戸常寿、鈴木おさむ、鈴木謙介、鈴木茂昭、鈴木秀美、
西土彰一郎、野崎圭一、旗本浩二、濱田純一、日笠昭彦、堀木卓也、村井純、吉田眞人ほか多数予定しております。
(敬称略:あいうえお順)


