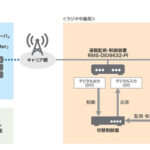放送100年 特別企画「放送ルネサンス」第35回

南海放送代表取締役会長
田中和彦 さん
田中和彦(たなか・かずひこ)さん。1954年1月18日生まれ。愛媛県伊予市出身。1977年 早稲田大学政治経済学部卒。同年4月 南海放送株式会社にアナウンサーとして入社。ニュースキャスターや野球・サッカーなどスポーツ中継、「POPSヒコヒコタイム」などの人気ラジオ番組を担当。編成局長、ラジオ局長、社長室長などを経て、2014年6月に南海放送 代表取締役社長、2020年6月に同社 代表取締役会長に就任(現在)。
田中和彦さん インタビュー
Contents
- 1 ご自身と放送とのかかわりについて
- 2 会長になった今も、ラジオの第一線で活躍中と聞くが
- 3 ラジオへの思いは昔も今も相当強いと感じるが、ラジオの魅力は
- 4 しかし、現実には特にAMラジオは経営的には厳しい状況にある
- 5 それは、AMラジオが経営の重荷だということか
- 6 AMは無くなってしまってよいのか
- 7 放送波を使わないラジオでも放送を呼べるのか
- 8 地域放送とインターネットとの関係は
- 9 しかし、時代の流れは放送と通信の融合に向かっているが
- 10 ローカル局の経営も厳しくなり統廃合も必要だという人もいるが
- 11 ローカル放送局が生き残るためには何が必要か
- 12 地域放送へのニーズはあると思うか
- 13 放送へのメッセージがあれば
ご自身と放送とのかかわりについて
中学3年生か高校1年生の頃、ラジオ番組の「オールナイトニッポン」をよく聞いていた。当時のパーソナリティの亀渕昭信さんに憧れ、志望する大学も変え、亀渕さんと同じ大学の放送研究会に入ろうと思った。しかし、当時は学生運動が激しくて放送研究会が休止していたためアナウンス研究会に入ることになった。
その後もラジオをやりたくて放送局を目指したが、放送局では、テレビの番組制作や報道など、色々な仕事があるため、ラジオのある南海放送に入ることにした。アナウンサー志望というよりラジオ志望であり、40歳まで、ラジオの深夜放送をやっていたが、その後もラジオ部門への異動希望を出し続けた。ラジオ・テレビ局におけるラジオの位置づけは、当時はテレビより低く、ラジオへの異動希望を出すと、「お前は何を考えているんだ」とまで言われた。ラジオ部門は赤字だったが、自分が好きで選んだ部門だから、何とか黒字にしたいと思い、必死にやった。
会長になった今も、ラジオの第一線で活躍中と聞くが
会長になってから、ラジオの現場に戻り、今も日曜日の朝に2時間の生放送をやっている。会長になって、ラジオ現場に立つことにしたのは、社長時代に、「ラジオはとにかく人手をかけすぎる、ワンマンでやるべきでディレクターはいらない。喋れるディレクターかアナウンサーにしろ」と言ってきたが、放送事故が怖いとか労働負荷が重いとかの理由で反対があった。
このため、会長になったのを機に、これまで言ってきたことが、実際に出来ることを示すため、ワンマンで始めた。「これで放送事故が起きたり、スポンサーが付かなかったりしたらやめる」と言って、半年やったら勿論無事故。今では6社もスポンサーが付き、レーティングも日曜日のプログラムでは、愛媛で一番だと自負している。
ラジオへの思いは昔も今も相当強いと感じるが、ラジオの魅力は
若い頃からラジオドラマを制作し様々な賞も受賞したが、ラジオの魅力は生放送にあると思う。ラジオドラマもそうだ。これまでに3回ほど、会社のホールに400人ぐらい一般のリスナーを集め、実際に生放送でラジオドラマをやった。生放送の緊張感を作り手や演じ手、それから観客であるリスナーも同時に感じてもらう。これこそラジオだと思う。
ラジオの本質はナマ。リスナーと共に作るのがラジオ。さらに、その盛り上がりや緊張感をスポンサーにも見てもらっている。現場には録音物は作るな、生放送で電話繋いでダイレクトに聞いたものを放送する方がビビットだ。「生じゃなかったらラジオはもう誰も聞いてくれないと思え」と言っている。
しかし、現実には特にAMラジオは経営的には厳しい状況にある
経営的に言えば、ラジオを続けるならば、出来るだけ早くAMラジオのFM転換なり、ネットのradikoに変え、AMを手放さないとやって行けないのが現実だ。私は社長の時に「ラジオ」という名前のついた部署名をやめ、radiko制作室にしてくれと言った。
結局、「メディア制作」になったが、その意味は、今後のラジオは、radikoに向けて制作し、それをサイマルで地上波にも出していく感覚でやることが必要だと考えたからだ。
それは、AMラジオが経営の重荷だということか
テレビ・ラジオ局の場合、テレビが良いときはラジオ部門が赤字でもよかった。私が入った頃の経営者は、ラジオは消防署のようなもので、決して儲からない。しかし、安全のために自治体が消防署を設置していることと同じで、赤字であってもラジオは必要だと言っていた。
しかし、テレビが少し厳しくなると、「ラジオの赤字は何だ」と言われる。その頃にラジオの部長になり、改革によってとにかく黒字にしようと努力した。
ただ、AMラジオは、設備の維持が経営にとっては負担になり過ぎる。
ラジオ経営の重荷がテレビを圧迫している。ヨーロッパはもうFMだけの形となって、おかげで世界的にAMの放送機器がどんどん値上がりしている。FMが300万円なら、AMは3000万円と桁が違う。コスト的にも見合わなくなっている。FMへの転換やネットへの移行を早く考えないと経営的に厳しいことは明らか。
AMは無くなってしまってよいのか
AMを止めるとなると必ず出て来るのが、災害時に大丈夫かという話しになる。しかし、それはAMを持つ放送局が、災害報道の出来る体制を整えているためで、FMになっても災害報道出来る体制があれば災害対応は出来る。伝達方法の違いを言っているだけで、災害報道が出来なくなるわけでない。
個人的には、AMラジオは、NHKが代表してやってくれればいいと思う。ラジオ放送開始の際のAMラジオの大事な「魂」は、NHKが継続してくれたら、それでいいのではないかと思う。

放送波を使わないラジオでも放送を呼べるのか
それは概念の問題で、現実的には、ラジオがない家がいっぱいあり、一方で、スマホはみんな持っている。こんな便利な文明の利器でradikoが聞けるのだから、それを使わない手はないと私は思う。先ほど話したように、radiko向けに放送コンテンツを作って、サイマルで地上波に流す、そのように考え方を変える必要があると思う。
地域放送とインターネットとの関係は
テレビとラジオでは異なるが、テレビで言えば、ネットは県外や海外にまで届くメディアであり、県域放送の立場から考えると、ツールとしての齟齬がある。その意味でも、テレビの県域放送がネットに置き換わるとは思わない。
そうではなく、ネット側にいる人の中から本当にテレビを見たい人をテレビに誘導する。そのためにネットを活用する。ネットでやって行こうとか、放送を止めてネットをやろうとは思わない。
しかし、時代の流れは放送と通信の融合に向かっているが
放送と通信の融合と言うが、放送と通信では、法律やルールが大きく異なっている。個人的には、その前に通信に対する規制をしっかりやるべきだと思っている。放送は、非常に厳しいルールがあり、わずか3秒でも放送が止まれば放送事故だという話になるのに、ネットならフリーズしても大きな問題にならない。それでは放送と通信の融合はうまく進まない。
「通信に規制をかけると民主的じゃない。自由を奪う。」という人もいるが、今の自由は恐ろしい自由だと思う。人を追い込んだりしている。
また、放送と通信を比較すれば、サブスクなどで音楽を聞いていると、突然CMが入るときがある。放送なら1曲終わったらCMが入るお行儀の良いやり方をする。トヨタのCMを流した場合、日産のCMはしばらく流さず間を開けるなど、放送は細やかな配慮するが、ネットはお行儀が悪い。
やはり規制をかけて、何がしかのルールを設け、放送に近い規制が出来てくれば、我々もビジネスモデルを壊さずに融合が可能になるかもしれない。
ローカル局の経営も厳しくなり統廃合も必要だという人もいるが
各キー局もここにきて、ローカル放送局の経営をどうするか真剣に検討を始めていると感じる。我々もローカル再編などの研究はしてきたが、その前にラジオの分社化も考えた。しかし、分社化するとローカルでは規模が小さすぎて経営が難しい。また、キー局の子会社になって支援して貰う方法もあるが、その場合、制作などの人員削減が行われ、放送局というよりキー局の支局のような状態になり、地域密着から遠くなる。
また、地域ごとに何県かを一つにまとめてしまう考え方もある。ホールディングスの下に2局をぶら下げ、ニュースネットワークは各キー局と繋がり、制作を一つにすれば効率化は図れる。いずれにしろ、放送収入が減少するなかで、よほど各局が放送外収入も含め力をつけないと、やっていくのは難しくなるだろう。軽局の経営も厳しくなり統廃合も必要だという人もいるが
ローカル放送局が生き残るためには何が必要か
コロナの時に、全国のコロナ情報よりも地元の現場の医師の話などの方が説得力あり、そうしたニーズがあることが分かった。
ローカル放送で重要なのは地域報道であり、ローカル放送が、災害時などにネットでは代替できない信頼性をどれだけ確保できるかが鍵となる。当社では、NHKよりも信頼できる存在であることを目指している。
何かあった時に、真っ先に見て貰えるようにすること、それができなければローカル放送の存在意味がなくなる。広い意味での生活情報も含むニュースで生き残っていくしかない。ローカル局のエンターテインメントは、キー局に負けるかもしれないが、報道は負けない。
現場には、NHKとの競争だと言っている。
ただ、報道は利益を生む部門ではなく、様々な形で、会社の利益を確保し報道を強化していくしか道は無い。スポンサー収入だけでなく、放送外も含め収益源を拡げないと沈む。
例えば地方自治体の広報制作の仕事や、自治体主催の運動会やイベントなどとも連携し収益につなげていく。我々は「愛媛主義」というキャッチコピーで、創業時から地域完全密着を掲げて取り組んでいる。
地域放送へのニーズはあると思うか
ラジオとテレビでは少し違うと思うが、例えばスポーツであれば、特に高校スポーツは相変わらず地域では盛り上がる。高校野球では、県予選は1回戦からラジオで全試合中継した。
その当時、甲子園でも夏は朝日放送、春は毎日放送から画面をもらい、NHKとは違って、地元の応援実況を付けて放送した時代もあった。ローカル放送は地域密接で地域を鼓舞する役割と考え、そうした地域のニーズに応えていくのが、かりやすいローカル放送の形だと思う。
放送へのメッセージがあれば
放送は、「わくわく」産業だ。「わくわく」を作り、人に「わくわく」して貰う。それが作れない人はだめだ。そうすれば、ネット動画に負けるはずがない。ネット動画に若い人が集まるのは、一時的な現象であり、テレビ離れは一時的なものだと思っている。それに飽きたら、本格的に考え作られた放送に戻ってくると思う。ただ、その時にちゃんとしたものを作っていなければだめだ。
この記事を書いた記者
- 放送技術を中心に、ICTなども担当。以前は半導体系記者。なんちゃってキャンプが趣味で、競馬はたしなみ程度。
最新の投稿
本企画をご覧いただいた皆様からの
感想をお待ちしております!
下記メールアドレスまでお送りください。
インタビュー予定者
飯田豊、奥村倫弘、亀渕昭信、川端和治、小松純也、重延浩、宍戸常寿、鈴木おさむ、鈴木謙介、鈴木茂昭、鈴木秀美、
西土彰一郎、野崎圭一、旗本浩二、濱田純一、日笠昭彦、堀木卓也、村井純、吉田眞人ほか多数予定しております。
(敬称略:あいうえお順)