
フォーラムエイト、地方創生・国土強靭化セミナーを振り返る
国土強靭化とデジタルを通じた地域振興へ貢献を目的に約2か月間にわたって全国で開催された「第7回FORUM8地方創生・国土強靭化セミナー」(フォーラムエイト主催、一般社団法人VR推進協議会後援)が閉幕した。
国土強靱化と地域振興への取り組みとの連携、特に各自治体におけるインフラ分野での取り組みへのデジタルを通じた貢献を目的に、2019年から全国中核都市で毎年定期的に開催している。また「国土強靱化とデジタル田園都市構想のDXによる推進」をテーマに、有識者による特別講演と併せて、設計・解析、3DVR、ICT活用各種システム等、デジタル田園都市構想実現を支援する同社最新の製品・ソリューションを紹介している。
今年は1月21日の福岡会場から3月19日の北海道・札幌市にかけて全国18会場で土木・建築業界や行政関係者など延べ625人が参加。各地ならでの取り組み事例を紹介したほか、登壇者と参加者による懇親会も開催され、盛況に終わった。
フォーラムエイトは、4月13日に開幕する大阪・関西万博に催事パートナーとして協賛。5月20日にテーマウィークでの未来の防災・減災に向けたトークセッションを提供するほか、5月1~6月1日にはロボット&モビリティーステーションでバーチャル体験ができるシミュレータシステムの展示「未来の月と宇宙のバーチャル体験」も予定している。

伊藤裕二社長にセミナーを終えた感想や万博での意気込み等を聞いた。
―全国18会場でのセミナーが終了した。あらためて振り返っての感想を
地方都市で開催するということで、できるだけ地方のユーザーに参加してもらいたかった。特に建設コンサルタントや建設会社もだが、ローカルの産業は地場にあることの意味が大きい。災害があればすぐに調査に行けるということもあり、普通の産業に比べて地方に点在している。
我々はソフトウェア企業で、ソフトウェアは実際に見たり触ったりしないとなかなか理解してもらえないことが多いのでセミナーは非常に重要な手段。ケーススタディを示すことでそれぞれの地域で使えるヒントになっていると思う。直接的なイベントで議論してもらうため、できるだけ重複しない形で開催しようと今年は過去最高の18会場で開催し、各地の事例を伝えることができた。
もう一つ、我々は技術を売っている会社なので、ソフトウェアに関する技術情報、サポート情報をプレゼンテーションを加えて紹介した。地方の政策は小選挙区出身の衆議院議員さんが詳しい。加えて地方の首長、市長さんにも登壇いただいた。地方振興で頑張ってらっしゃる中、我々もDXの力で応援していきたい。我々は元々公共事業の設計からスタートしているが、今はVRやメタバースで可能性も広がっている。
―昨年は能登半島地震から始まり、各地で災害が多発した年だった
石川の金沢でも開催して、復旧支援の設計を担当するコンサルの方にも話を聞いたが大変だと聞いた。道路についてはがけ崩れや途絶といった問題があった一方で、橋梁など公共の主たる構造物は比較的損傷を受けずに済んでいた。
神戸の震災以降、耐震設計や診断技術が急速に発展し、我々もソフトウェアに反映することでユーザーもそれを使って新しいものや補強を進めていたことが影響したと考えている。石破総理も国会演説で、技術基準の強化について話していたが、きちんとした基準、特に技術基準を策定し、適用していけば、防災や減災に繋がるということがわかってきている。
ただ遅れているものは遅れている。例えば警戒ルート。地震発生時に、災害派遣とか、物資搬入のための道路などを精査して、どこを使うかをソフトウェア的に判断できる技術がある。ナビゲーション技術を使って関東で開発したものだが、石川、能登地域の場合は道路網がなくて難しく、そういったことがほとんど考えられていない。ガイドラインを作って国が自治体に対策を指導し、それを受けて自治体も予算をつけるといった動きが必要。
―全国で山火事も多発しているが、その場合の避難予測もできるのか
可能だがある程度開発していないとそういうシミュレーションはなかなかできない。今度の万博でも登壇されるガリア教授が今まさに取り組んでいる。イギリスの国家プロジェクトで数十億くらいの予算がかかっている。地元の消防局が取り組み、山林火災や避難、被害想定のシミュレーションを進めているがかなりの予算が必要。めったに起きないためそこに大きな予算がつきづらい。実際にシミュレーションしようと思うと、川のような一次元構造物だとどこで破堤するのかいくつか想定できるが山だとどこから火が出るかわからない。膨大な解析が必要となるが地方だと予算がないと厳しい。
―建設現場のDX化について
地方自治体にしても取り組みが多方面に渡っている。あるところではメタバース、あるところでは防災減災を実現しようとして、いい事例があるともっと工夫して、もっといいものを作ろうとやっている感じはある。例えば除雪シミュレーターを使った取り組みやメタバースを使った観光振興。ただ徐々にしか進んでいないのが現状。一律的にやれるものではない。国が主導してるものは予算も出しやすいので積極的という印象がある。
―今後取り組みを加速させていくにはどうすればいいか
日本の場合、公共事業への予算が限られている。G7プラス韓国で一番伸び率が低いのは日本。韓国とか欧米もどんどん伸ばしてGDPも上がっている。お金になるところに投資するみたいなとこはあるので、どうしても予算がつかないと企業が入っていくことは難しい。
インフラは100年や200年先の投資に向けた予算を抑えておかないと国は発展しない。例えば日本の橋梁の6割は耐震診断して施工しないとだめだと言われているが、50万近くの橋梁のうち70%以上はそういうことができてない。地方自治体も多くの橋梁を抱えているが予算がなくて廃止する橋梁も出てきている。
―今後の大規模地震を想定して目指すところはどこか
FEM構造解析とかソフトウェアの高度化によって安全性の調査性能は上げることができ、補修して使えるかどうかの判断ができる。全部を壊してもう一度作り直す場合にはものすごいコストになるが、調査の性能を上げることで補修補強だけで対応できたり、あるいはほとんど補修しなくても済むというケースも出てくる。
一つの証明として、神戸の震災後に防災科研が「E-ディフェンス」という実験施設を作ったが、そこでは建物を振動台に乗せてどこが壊れやすいかを調べることができる。建物の破損や変形などを予測するソフトウェアの国際コンペをやっていて、15社くらいが参加した中でうちのFEM解析ソフトは2年連続優勝したことがあった。積極的にソフトウェアの精度を上げるよう開発を重ねることで経済設計にもつながるし安全性を高めることにもなる。
―いよいよ万博が開催される。フォーラムエイトは催事パートナーとして参加し、5月20日にはテーマウェークでの「あなたの安全・安心な未来に向けた災害大国である日本だからこその世界への提言」を予定している
登壇する東北大学の今村文彦教授も、グリニッジ大学のエドウィン・R・ガリア教授も防災や避難の分野では世界でもトップクラスの研究者。我々が一番得意なシミュレーションやバーチャルの切り口で、日本を基軸に、世界に防災減災や避難について提言したい。
基本的に、災害はなかなか体験できないのでバーチャルで体験してから初めて気付くことがある。この気付きを防災に対する保護対策に役立てるためにはシミュレーションが必要。我々としては、デジタルやシミュレーションを使った防災支援を提言したいと思っている。
―5月1日~6月1日にかけてはロボット&モビリティステーションにも出展する
ロボットモビリティはロボットとモビリティ、いわゆるシミュレーター。最初はロボットだけだったのをモビリティも入れてくれて、未来の月と宇宙のデジタルツイン体験というテーマで、いくつかシミュレーターを設置する。例えば月面の6分の1の重力をヤリスで走ったらどうなるかとか。自動車会社からの提案で彼らが持ってる車両運動モデルと月面の観測写真を組み合わせてシミュレーションしたものとかを置いている。このほか宇宙飛行士のような360度の仮想無重力での船外活動とかも体験できる。体験型なので人気が出ると思うのでぜひチャンスがあれば来て欲しい。
―あらためて万博に向けた思いを
私は神戸出身で、中学1年のときに万博だった。2回行ったけど、まともに見れなかった。せっかく同じように開催されるので少しだけでも参加したいという思いがあった。今度は落ち着いて何回も見に行きたいと思っている。関西圏では社員旅行に万博という声もある。個人的に落合陽一さんのエリアとかは行ってみたい。前回同様、オリンピックの後に万博というパターンを踏襲している。大阪は東京に次ぐ都市であり、地方振興から、ひいては全国につながって盛り上がってほしいという思いはある。
―最後に万博来場者にメッセージを
イベントなので楽しんで来ていただきたい。気候が印象を左右するのでちょうど我々が参加しているようないい時期に来てもらえたら快適だと思う。社員もサポートに入って頑張るのでロボティクスモビリティにも寄ってもらえたら。
この記事を書いた記者
- 主に行政と情報、通信関連の記事を担当しています。B級ホラーマニア。甘い物と辛い物が好き。あと酸っぱい物と塩辛い物も好きです。たまに苦い物も好みます。
最新の投稿
 PR記事2025.04.18フォーラムエイト、地方創生・国土強靭化セミナーを振り返る
PR記事2025.04.18フォーラムエイト、地方創生・国土強靭化セミナーを振り返る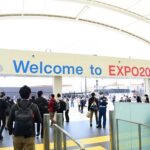 レポート2025.04.18大阪・関西万博メディアデー体験レポート【NTTパビリオン】
レポート2025.04.18大阪・関西万博メディアデー体験レポート【NTTパビリオン】 行政2025.04.18検索拡張生成品質向上向け共同研究、NICTとTDSL
行政2025.04.18検索拡張生成品質向上向け共同研究、NICTとTDSL 行政2025.04.16第70回前島密賞受賞者一覧
行政2025.04.16第70回前島密賞受賞者一覧


