
電気通信普及財団・守屋理事長インタビュー「若手研究者の活躍・基礎研究に光を」
電気通信普及財団は1984(昭和59年)、当時の郵政大臣の許可を得て、電電公社(現NTT)による寄付で設立。情報通信分野の研究調査助成や援助、表彰等を中心的な事業として活動。2013年に公益財団法人として認定され、昨年2024年に設立40周年の節目を迎えた。専務理事として5年間にわたり財団を支え続け、昨年7月1日付で理事長に就任した守屋学氏に就任の思いと今後の事業活動について聞いた。
―昨年7月1日、電気通信普及財団の理事長に就任された時の率直なご感想と就任から約9カ月経過しましたが、これまでの手ごたえをお聞かせください。
私の場合、専務理事からの昇格というこれまでにない任命の形でしたが、専務理事の後任が空席となったため、両方兼務しながら充実した時期を過ごさせていただきました。特に昨年度は、当財団創立40周年という節目の年で、周年記念企画として、記念助成プログラムやこれまでの助成援助・表彰実績集を電子ブックで制作しました。どなたでも見れるように一般公開したのも大きかったと思います。
また3月には、例年行っている贈呈式の対象者にも参加いただいた記念式典を行い、多くのご来賓にご臨席いただき、温かいお言葉も賜りました。まず、そうした特別な年を、理事長として迎えられたことを大変光栄に思いました。そして、財団の長い歴史と伝統を受け継ぎ、社会経済の基盤である情報通信研究発展の一助になるという財団の社会的意義と責任を痛感し、また次の10年に向けて、新たな助成援助・表彰のあり方を追求し始める、という身の引き締まる思いも改めていたしました。
―これまで専務理事として5年間務められていたと聞きます。振り返ってみていかがですか。
ナンバー2として5年間にわたり、2人の理事長に仕えてきましたが自分が理事長になるとは思っていませんでした。常勤の理事は代表理事に当たる理事長と業務執行理事に当たる専務理事の2人しかおらず、昨年は兼務だったので苦労しました。
これまで例年通りの助成や財団表彰をしてきましたが、コロナ禍の時が一番しんどかった思いがあります。大学キャンパスも活動制限によりロックアウトとなって研究活動が低調となり、海外で研鑽をつむ機会が失われてゼロに近い年もありました。
そこから比べると今は応募数もほぼコロナ前と同水準に戻り、カテゴリーによってはコロナ前より増えているところもあります。特に海外の渡航応募は顕著になっていていい状況になってきています。ただ円安ドル高が続いたことで円建て留学は資金的に大変だったと思います。
コロナ期間中の工夫や知恵としてリモートワークが盛んになったことは研究活動にとって大きかったと思います。従来はシンポジウムや学会でも集まる必要がありましたが、小規模なハイブリッド開催などリモートによる効率化が確立しました。助成や援助を受ける研究者は所属もバラバラですが、リモートによってコラボレーションがうまくいくこともあります。我々財団の審査委員会も以前は集まっていましたが、コロナを期に半分以上がズームに代わりました。
―財団に入る前はNTTにいらっしゃったと聞きます。
NTTで20年勤め、その後はNTTドコモで11年働きました。NTTでは主に財務系、当時は経理部として資金運用と調達実務をやっていて、そこでの経験は財団でも役に立ったと思います。ドコモでは主に金融事業として、クレジット事業や電子マネー事業の立ち上げに携わり、非接触ICを使ったモバイルマーケティングなどをしていました。
NTT時代の後半から新しい仕事を始めることに関わり続け、財団でも学際研究賞という文系理系をまたがる新しい賞を作ったり財団と関わってきた人々とのコミュニティを立ち上げたり、新しいことにも取り組めてきたと思います。その分実務担当のスタッフには苦労もかけたと思いますが。
我々はどちらかというと小規模な助成援助枠なので、学生からシニアな研究者までステージに応じたプログラムを示したりコミュニティを通じて研究者同士が情報交換を通じて自然発生的にグループを作って応募するきっかけにしてほしいという思いもありました。
―既存の財団の事業について「重点項目」 をお聞かせ下さい。また2024年度の財団賞の総評、2025年度の財団賞の期待するところをお聞かせ下さい。
電気通信普及財団の事業においては、「研究調査助成」と「電気通信普及財団賞」が代表的な事業となります。
「研究調査助成」は、情報通信に関する研究調査に対する助成です。助成額は年300万円程度まで。助成期間は原則1年間、必要があれば3年間も可能です。1984年の財団設立初年度より事業を開始し、40年間に3629件に対し、約45億円の助成を実施しています。
2024年度においては、通常の応募に加え、40周年記念枠「A I時代のデジタル社会 (技術・課題)」の募集を行ったところ、新規の申込件数が5割増の255件、総額約5億円に及び、全体として154件、2億5984万円が採択されました。
「電気通信普及財団賞」は情報通信に関する優れた著作や研究論文を毎年度表彰しています。こちらは設立2年目の1985年に開始し、これまで約1000件の表彰を行っています。
人文学・社会科学分野、技術分野、両分野にわたる学際分野の3分野について、本賞と学生賞を設けています、毎年多くの学生も挑戦しています。
これらの他にも多様な助成援助プログラムを用意し、博士課程学生等の若手から、精力的に研究に邁進される中堅、研究成果の普及に努められる指導者層など、研究者人生全般に寄り添えるよう事業を進めています。
(全文は4月30日付紙面に掲載)
この記事を書いた記者
- 主に行政と情報、通信関連の記事を担当しています。B級ホラーマニア。甘い物と辛い物が好き。あと酸っぱい物と塩辛い物も好きです。たまに苦い物も好みます。
最新の投稿
 情報通信2025.04.30電気通信普及財団・守屋理事長インタビュー「若手研究者の活躍・基礎研究に光を」
情報通信2025.04.30電気通信普及財団・守屋理事長インタビュー「若手研究者の活躍・基礎研究に光を」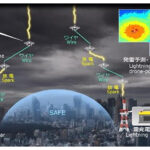 情報通信2025.04.30ドローンによる雷の誘発実験に初成功
情報通信2025.04.30ドローンによる雷の誘発実験に初成功 行政2025.04.30「SecHack365」受講生募集
行政2025.04.30「SecHack365」受講生募集 情報通信2025.04.30低軌道衛星とスマートフォンのビデオ通話に成功
情報通信2025.04.30低軌道衛星とスマートフォンのビデオ通話に成功


